日本各地には、土地の気候や地理、歴史文化、地域情勢などと密接な関係を持った民藝が点在する。伝統的なものから新しいものまで実に多彩だ。大量生産型の工業製品にはない、見えない背景が生産物の数だけある。そうした民藝ができあがるまでの物語を連載では追っていきたい。前回に続き、独自の道をひた走る美濃和紙の紙すき職人・千田さんから、これまでの経緯について話を聞いた。
▶vol.1の記事はこちら
村をつくりたくて
日本に帰ってきた
前回の記事で触れたように、千田さんはアーティスティックな和紙作品も生み出している。時代が狂いそうな不思議な出で立ちだからか、余計に彼の芸術性や思想が気になるのかもしれない。ひとまず、学生時代の話から今に至るまでを聞いてみることにした。

「学生時代はクラブカルチャーというか音楽とかファッションに単純に興味があって、東京にいるときからクラブばっかり行っていました。ロンドン発の音楽が多かったので、ロンドン自体に興味が湧いて行ったのが最初ですね。海外では、『スクワット』って言って、不法占拠された家に人が勝手に住みついているようなところでパーティーに参加してました(笑)。社会のド底辺みたいな集まりなんです。ヒッピーとか、アル中の人とか、社会に反抗しているような人たちがいました」
こうした海外生活の傍ら、当時働いていたレストランでのある経験が、今の暮らしへとつながるきっかけになっていく。
「ロバート・デ・ニーロがオーナーをやっているレストランで働いていました。マイケル・ジャクソンとかマドンナみたいなセレブが来るところだったので、普段行っていたパーティーと職場の落差が激しすぎましたね(笑)。お店に食材の銀鱈がどんどん送られて来ているのを見て、『こんなに使ってたら海から銀鱈がいなくなるんじゃないかな』みたいなことを思って。『ちょっと都会ヤバいんじゃないの』と疑問を感じるようになりました」
このころから、“南米”、“シャーマン”、“民族”といったキーワードに惹かれるようになり、千田さんは南米行きを決意する。そして、現地で目にした人々の暮らしは、その後の人生に大きな影響を与えるのだった。
「手仕事しかないし、電気もガスも水道もないけど、みんな豊かに楽しそうに暮らしていて、『なんなんだこれは』みたいに思いました。みんなで助け合って好きなときに好きなことができるコミュニティを自分でつくれたらいいなと考えるようになって、『村をつくりたい』と思って帰国しました。ただ、日本に帰って来てからすぐは行き場所がなかったので、実家の近くにあった薬膳料理のお店で働きはじめたんです。そこで奥さんと知り合って、意気投合して、水のきれいなところを探して一緒に美濃へ」
不純な動機ではじめた
紙すきの仕事

美濃に来てから、掛け持ちできる仕事を探すためハローワークへ赴き、そこで見つけたのが“紙すき体験指導”の仕事だった。
「面白そうと思ってはじめたのがきっかけです。でも、市の施設だったこともあって会社員みたいな働き方が合わなくて、しばらくして辞めてしまいました。あるとき、自分で雑誌の切り抜きを貼っていく“コラージュセラピー”を受けたんですけど、『あなた、師匠を求めてるわよ』『手に職をつけたがってるわよ』って言われて、『俺の潜在意識はそういうふうなんだ~』と思っていたら、その日の夜にある電話がかかってきたんです。『80歳になる紙すき職人さんが後継者を探してるんだけど、誰かいない?』という話だったので、これは自分がやるしかないだろみたいな(笑)。本当は自分の知り合いで誰かいないかって電話だったんですよ。向こうもまさか俺がやるって言うと思わんかったと思います。紙すきをやるには不純な動機だったんです」

こうして、本格的に紙すきの道を進むことになった。実際に師匠のもとで働いてみると、それまでとは違う感触があったと千田さんは当時を振り返る。
「『あ、これだ!』と思える働き方でしたね。南米じゃなくても、日本の近くにこんなところあったんだって。住むところと仕事をする場所が同じなのがいいなと思いました。自然の中だし、山から恵みを受けている水を使っているし、火も木も使うし、『これ仕事でいいの?』みたいに思ってました(笑)。廃れてしまった業界ではあるので、心配してくれる人は多かったですけど、自分自身に不安はなかったですね」

修行の日々は約2年半続いた。職人の世界で師匠というと、頑固で怖いイメージがあるが、千田さんと師匠は相性が良かったようだ。
「この工房からすぐ近くのところに住んで、歩いて通っていました。週5日、8~17時くらいまで。師匠と一緒に仕事をしながら作業を覚えていきました。最初の方は紙をすく機会をもらえなかったんですけど、途中からやらせてもらえるようになって、とにかく毎日紙をすいてました。失敗もめちゃくちゃしてますよ。1枚の紙の値段がものすごく安い薄利多売な仕事だったんで、毎日大量の紙をすきまくって仕事を覚えていった感じですね」

「師匠は頭が柔らかくって、新しいことにも挑戦して、思いついたことをやってみようという人でした。俺の挑戦したいこともすんなり受け入れてもらったし。職人さんって『これはこうしないかん』みたいな人が多いですけど、自分の師匠には柔軟に受け入れてもらったので、一緒にやってこれたのかなって思います」

そして、ついに継承の日が訪れたのだった。
「あるとき師匠から『あんたつぎゃあ』(あなたが継ぎなさい)みたいなこと言われて。工房も買ってくれということだったんで、『買う?あ、はい…!』みたいな感じで(笑)。ついでに雇ってくれとも言われたので、『そんなことある?』ってびっくりでした。いきなり立場が逆になるので、覚悟を決めてやるしかないなと思いましたね」
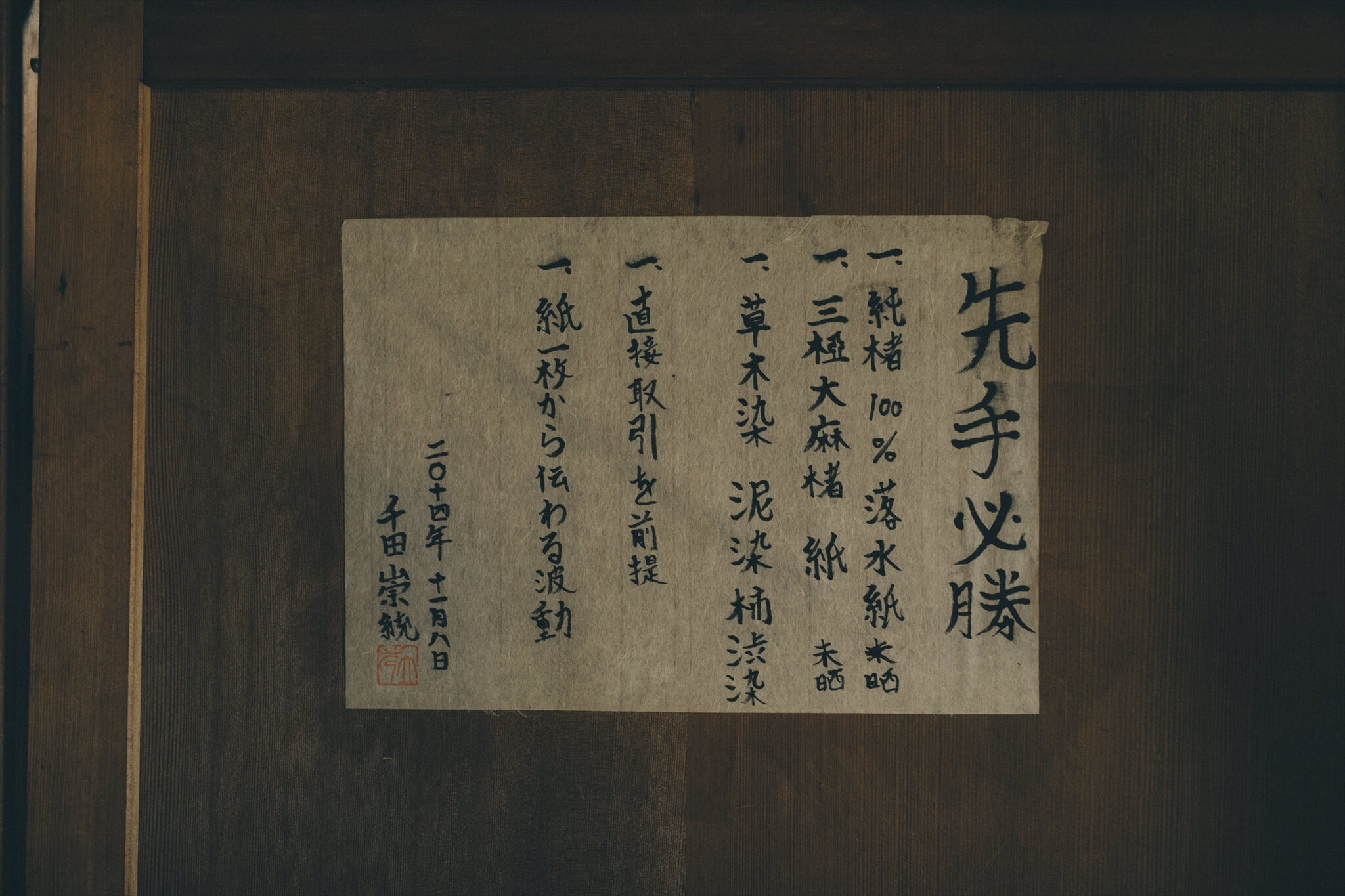
工房を継いだことで責任感は大きくなったものの、自由が増えて楽しくなった面もあったようだ。もちろん、自分が稼がなければいけないというプレッシャーも大きく、無理をして働きすぎてしまったと千田さんは話す。そして、ある事件を引き起こしてしまった。
「朝起きたら手紙と通帳と携帯を置いて奥さんが家から出て行ってしまったことがありまして…(笑)。薄利多売でめちゃくちゃ毎日忙しく働いていたことに対して、『あなたは本当にそういうことやりたいわけじゃないでしょ?』と。それを機に路線を確認して、今のやり方に変えていきました。それまでは塩素漂白したり、楮を煮るときの薬品も結構強いものを使っていたんですね。工業的なやり方に近かったんで、漂白せずに手でちり取りをするような昔の製法へ戻しました」
アート作品に挑戦するようになったのもこのころからだ。通常の和紙に比べて、和紙アートの出る数は少ないが圧倒的に単価が高くなる。薄利多売の和紙づくりを続けるより、自分も家族も納得できる状態に近づける。そんな経緯もあって、今の千田さんの制作スタイルが生まれたのだった。
これ、植物なの?
「本美濃紙」は茨城県産「大子那須楮」(だいごなすこうぞ)のみ、「美濃紙すき和紙」は国産原料のみの使用が条件となっている。楮は高知や茨城、新潟などの数少ない産地から送られてくるというが、そもそも楮の生産量は減っているのが現状だ。かつて美濃和紙の原料は周辺の津保川流域に生えている“つぼくさ”なる植物を使っていたともいわれる。近くの地域から原料を仕入れて、美濃は紙すきに特化していたと考えられている。それが今では、楮の栽培にまで関わる紙すき職人が現れているのだそうだ。実は千田さんもその一人なのだ。
「地元で楮の栽培から収穫までしている『美濃市こうぞ生産組合』があります。もともと紙すきの人なんて誰も組合員ではなかったのですが、組合員の高齢化が進みすぎて楮畑が管理できないという話になっていたんで、『なんとかしないと!』って自分が入ってたんです。生産した分は美濃の紙すき職人さんが買ってくれるので、それでほとんどなくなります」
千田さんは昨年まで穴洞支部の支部長を務めていたというが、今後は自分の分は自分で栽培するやり方に少しずつ変えていくそうだ。

「ちょうど工房の近くに楮畑があって、森林研究所が研究の一環として使っていた畑なんですけど、そこは持ち主がいない状態の土地なんです。それで、弁護士事務所の人がそれを売りたがってるから誰か買わないかって話があったので、「俺買いたい!」って手をあげました。師匠の工房に続き、また買わないか案件ですね(笑)。今年の12月に今生えている楮を刈り取る予定です(2021年10月取材時点)。刈り取り終わったら本格的に自分で手入れできるようになるかな」

自分の畑を所有し、楮の生産まで手を広げつつある千田さん。紙すきをはじめて11年目になる。いくら経験を積んでも、はじめたときから変わらない感覚があるという。
「『これ、植物なの?』とはずっと思いますね。紙を見て植物を連想しなくないですか?その不思議さというか面白さというか。だからそのあいだを作品で表現したいなと思います。植物でできていることをもっと知ってもらいたい。単純に面白いんで」
そして思いは植物から、山にまでつながる。

「紙すきは水がないと仕事ができないんですけど、川の水位が昔より減ってるとか、前はスギやヒノキがこんなに植えられてなくて、裏山に行って薪にする広葉樹を伐っていた話を聞いたことがありますね。もうちょっと昔の山に戻したいな。自分たちが使っている水は山から来ているので。もう少し保水力が増えて、いろんな植物が棲める山になったら俺もうれしいし。それがまた仕事につながってくるって考えるといいかな。山の木を使ってみんなで遊んで、ときどき楮の畑へ行って、紙すき体験もできて。そんな“紙すきテーマパーク”みたいな場所をここにつくれたらいいなと思ってます」

和紙と山を結びつけられる人は意外に少ないのではないだろか。確かに原料は山に生えている木なのだが、和紙を目の前にすると、その事実はどこかへ吹っ飛んでいってしまう。けれど、毎日たくさんの水に触れ、楮の繊維を手にしているつくり手は、山のことを考えないわけにはいかなくなるのかもしれない。なぜなら、それらがなければ自分の仕事ができないからだ。
千田さんのようなつくり手の話を聞くことで、彼らに見えている世界を、私たち(使い手)も少し覗かせてもらっている気がする。見えていない世界をちょっとでも知りたくて、民藝ができあがるまでの物語を追ってしまうのだろう。
さて、美濃和紙の物語はここで終わりではない。もう一つの地点へ移って、旅を終えよう。
▶vol.3はこちら
- ●Information
- Warabi Paper Company
- 〒501-3788 岐阜県美濃市蕨生725-1
- 営業時間:9:00〜17:00、土日祝日定休
- 0575-34-0310
- https://warabipapercompany.com/












