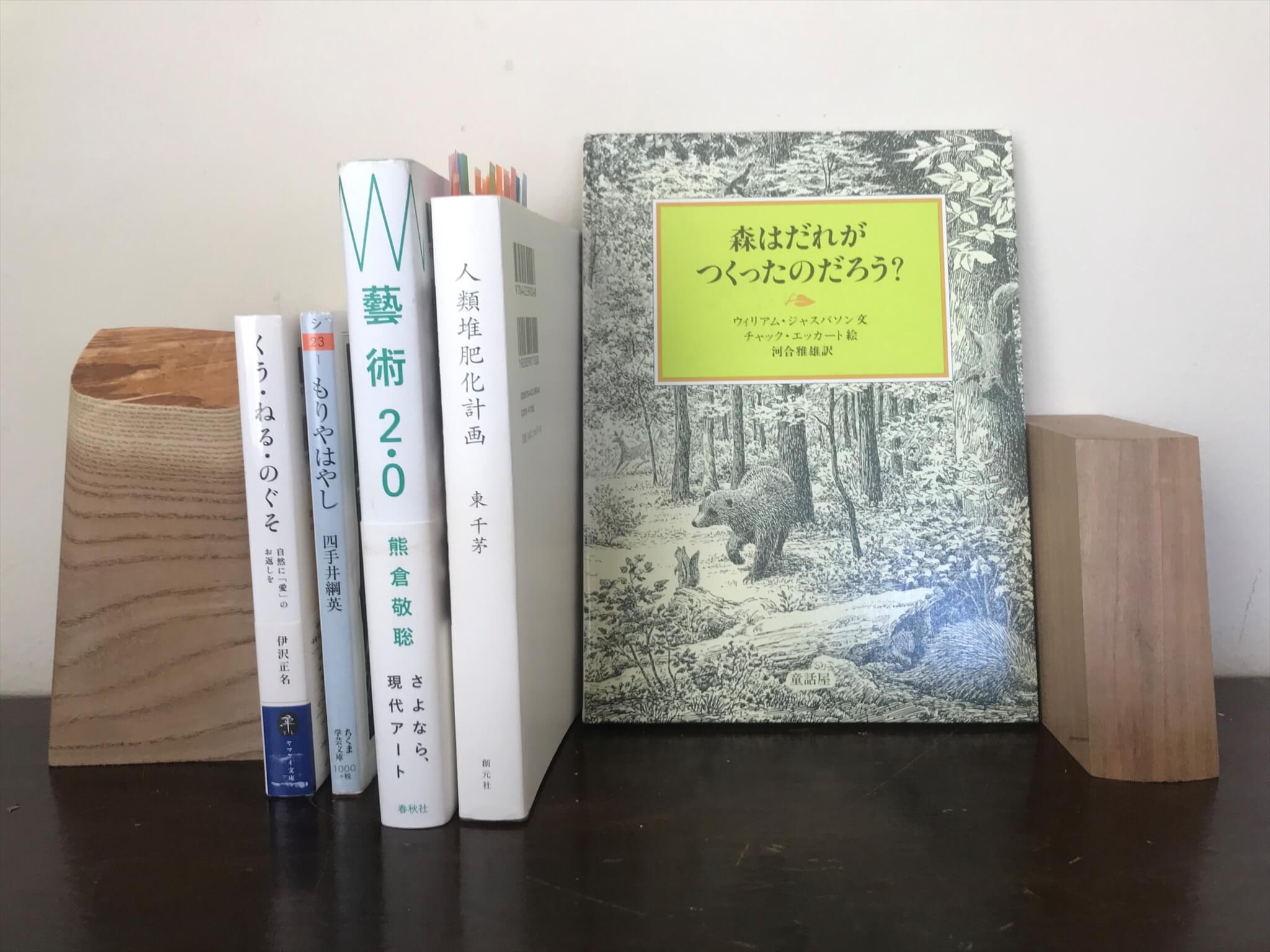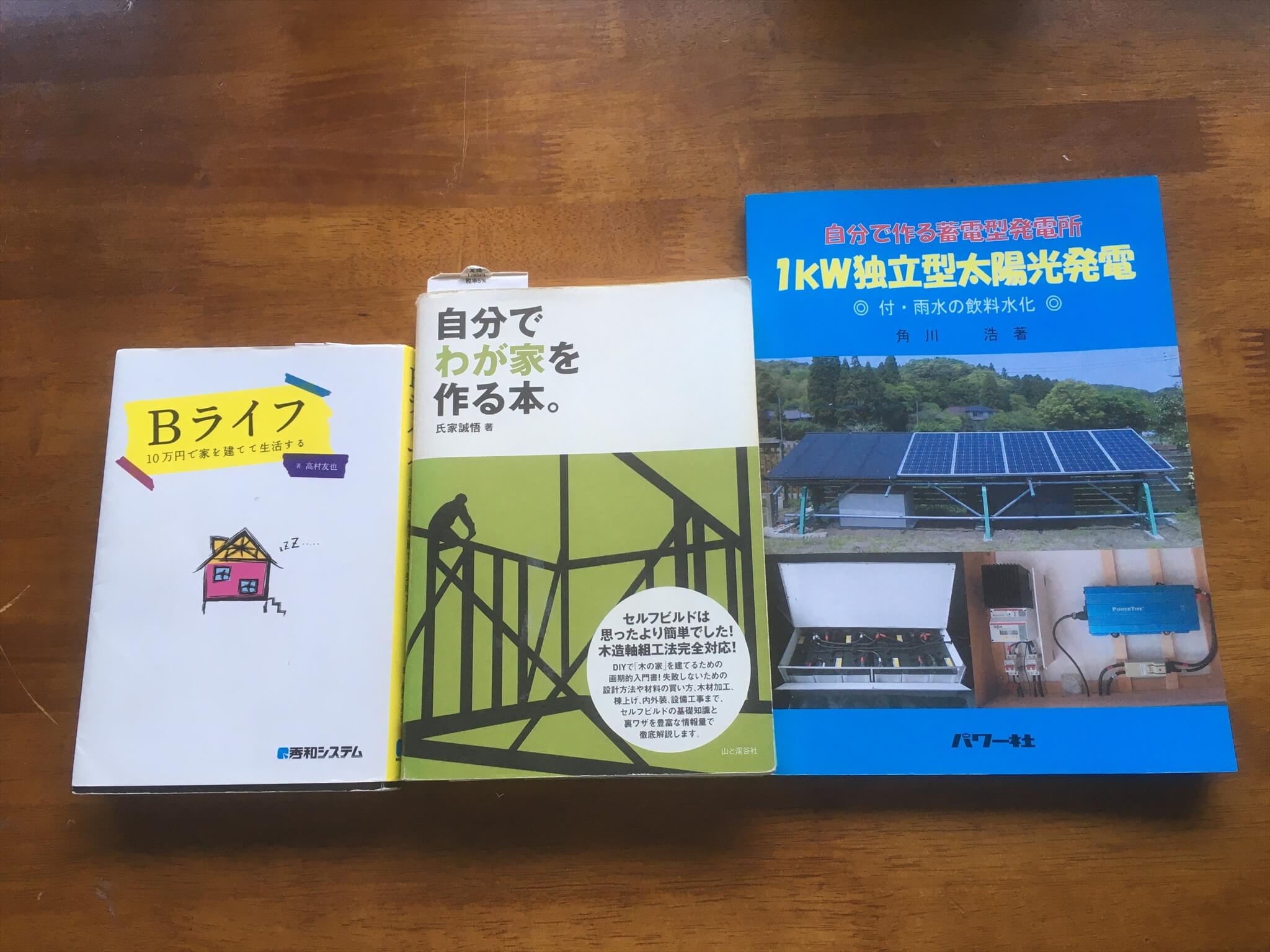森の中には何か不思議なものがあるーー「本」と「映画」に潜むラビリンスにはどっぷりはまり込む当連載「Memento Mori」。深い森についての映画と本を毎回1冊ずつ取り上げ、テーマに合わせて読み解いていく。今回は「夢中にさせる森」
鳥を追いかけ
北米大陸を駆けめぐる
「アメリカ人は何でも競争にする」
『ビッグ・ボーイズ しあわせの鳥を探して』で、とある光景を見た人がこう嘆くシーンがある。たしかにあまりにも熱狂的で、滑稽だったりもするのだが、モチーフとなっているその競争はどうやら本当にあるらしい。「ザ・ビッグイヤー」、北米大陸で1年間に見つけた野鳥の種類を競う、バードウォッチングのコンテストだ。バードウォッチングというと、森や水辺など自然のなかで望遠鏡やカメラを手に野鳥を観察する、のんびりとしたイメージがあるかもしれないが、ここで描かれるのはそんな穏やかなものではない。江戸時代の庶民が「一生に一度はお伊勢さん」と夢見たように、鳥好きにとっては一生に一度、参加できるか否かのイベント。広大な北米大陸を駆けずり回って、時間とお金を注ぎ込むことになるその一年は、その名の通り、何ものにも代えがたいビッグイヤーなのだ。

常軌を逸した大会に参加する面々は、本気度が違う。鳥にかまけて離婚し、実家暮らしをしている勤め人のブラッド(ジャック・ブラック)は、親に借金をして小言をいわれたり、上司から無理やり休暇をもぎ取ったりしながら、優勝を目指している。そのブラッドに立ちはだかるのが、過去に驚異的な最高記録を打ち立てたボスティック(オーウェン・ウィルソン)。彼もやはり鳥が原因で、離婚を2度経験。子どもを欲しがっている現在の妻とは「今年こそ」出場しない、と約束したものの、自分の記録が破られないか心配で、結局、例年通り鳥を追いかけてほとんど家に帰らない。ニューヨークの大企業の社長であるスチュー(スティーブ・マーティン)は、愛する妻に背中を押され、長年の夢を叶えるべく参加。資金も潤沢な彼は、社長業を早々に引退して大会に専念したいところなのだが、部下に泣く泣く引き止められている。

季節や気象条件、さらにバーダーたちの情報網によって、北米大陸広しといえども、彼らが訪れるポイントとタイミングが重なることは珍しくない。そしてそこでは熾烈というか、大人げない駆け引きが繰り広げられる。特にボスティックはこずるいところがあり、スチューを船酔いさせて、集中できないように仕向けたり、鳥を探し出すまでの面倒なところは他人まかせにして、成果だけをかっさらおうとする。大会に参加していることをみな隠そうとするのも厄介で、いつどこに行ってもほとんど同じ顔ぶれなのに、”ビッグイヤーに参加していない、ただの鳥好き”を装いながら、ライバルたちの記録を気にしている。

そうやってなりふり構わず行動するところも含めて、彼らの情熱には恐れ入る。嵐の襲来で、無数の鳥が地上に降りてくる珍現象がテキサスで起こる情報をつかめば、仕事や家庭を放り出して一目散にその地を目指す。そうかと思えば、週1回しか飛行機が飛ばず、ホテルもレストランもないアラスカ州のアッツ島が、5月限定で鳥とバーダーで溢れかえる。低木しか生えない凍土に覆われた大地を自転車で疾走し、雪深い森を長時間歩き、鬱蒼としたジャングルをボートで進み、断崖絶壁の間をヘリコプターですり抜け……。鳥を見るためならどこへでも出かけ、どんな苦労も惜しまない。彼らを駆り立てるのは、純粋な鳥への愛なのか、はたまた名誉欲なのか。希少種をついに見つけた喜びと、なぜかふと去来する一抹の寂しさと。情熱は代償なしには続かないことも教えてくれる。

『ビッグ・ボーイズ しあわせの鳥を探して』
監督:デヴィッド・フランケル
製作年:2011年
製作国:アメリカ
ディズニープラスの「スター」にて配信中
情熱を受け止め
進む道を示してくれた森

森に魅せられた写真家は数多くいるが、『そして、ぼくは旅に出た。 はじまりの森 ノースウッズ』の著者、大竹英洋氏もそのひとり。彼は撮影20年の集大成とされる、自身初の本格写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』で、2021年に第40回土門拳賞を受賞している。ノースウッズ(North Woods)とは、「北アメリカ大陸の中央北部に広がる湖水地方を指す呼び名」なのだが、地図上にその地名が記されているわけではなく、日本人にとっての「雪国」のように、ロマンや郷愁を誘う言葉らしい。かくいう著者も、ノースウッズの魅力にすっかり取り込まれてしまうわけだが、本作はやがて通うことになるノースウッズを初めて旅した日々の回想録となっている。
そもそも日本人にはほぼ知られていないノースウッズを、大学を卒業して間もない大竹氏が目指したのは、ひとりの写真家に弟子入りを直談判するためだった。彼の名前は、ジム・ブランデンバーグ。『ナショナル・ジオグラフィック』の表紙を何度も飾り、オオカミの写真を撮り続けていることでも知られる、世界的な自然写真家だ。大竹氏はある晩見たオオカミの夢に導かれるようにして、ジムの写真と出会い、彼のもとで写真を学びたいと思うのだが、それまで写真について学んだことはなく、一眼レフカメラを持ち始めたのは、わずかその前年……。なんという無鉄砲さと青臭さ! しかしこの無鉄砲さと青臭さを武器に(と、当時の本人はもちろん思っていないが)、熱い想いを着々と行動に移していく大竹氏が、なんとも眩しく見えてしまうのだ。

そうはいっても彼自身、弟子入りを断られるであろうことは百も承知している。だからこそ、憧れのノースウッズで夢見心地な気持ちを少しでも長引かせるために、ジムが住んでいると思われる場所まで、キャンプをしながらカヤックでゆっくり時間をかけてアクセスしようと考える(これまで井の頭公園の貸しボートくらいしか漕いだことがないのは、さておき)。こうして、たったひとりで森と湖の世界へと漕ぎ出すのだが、最初は恐るおそるだった心が徐々にほどけ、大小さまざまなハプニングが少しずつ、でも確実に彼を逞しくしていく。
湖と湖の間にあるポーテッジ(陸の道)をカヤックと荷物を背負って運んだり、見知らぬ水鳥の鋭い鳴き声に驚かされたり、“釣りの虫”がうずいて試してみたところ、これまた見たことのない不気味な風貌の魚が釣れて、途方に暮れたり。8日間にわたるカヤックの旅だけでも、読んでいる側としては充足感に包まれるのだが、その後のジムとの緊張の対面、さらに犬ぞりによる南極横断を世界で初めて成し遂げた、極地探検家のウィル・スティーガーとの出会いによって、大竹氏はひと回りもふた回りも成長する。そして写真を撮るとはどういうことなのか、構図や光の向きなどテクニック以前に大事なことを、身をもって学んでいく。
文庫版あとがきで、大竹氏は次のように記している。「あの日、未知の世界へ一歩を踏み出した自分自身に「ありがとう」と言いたい」。夢を思い描くだけなら誰でもできる。大切なのは、夢を実現させるために行動を起こせるかどうか。その行動力を「若気の至り」と都合のいい言葉で呼んで、高みから見下ろすのはつまらない。一歩を踏み出す「あの日」が今日になる可能性は、生きている限りあるはずだから。
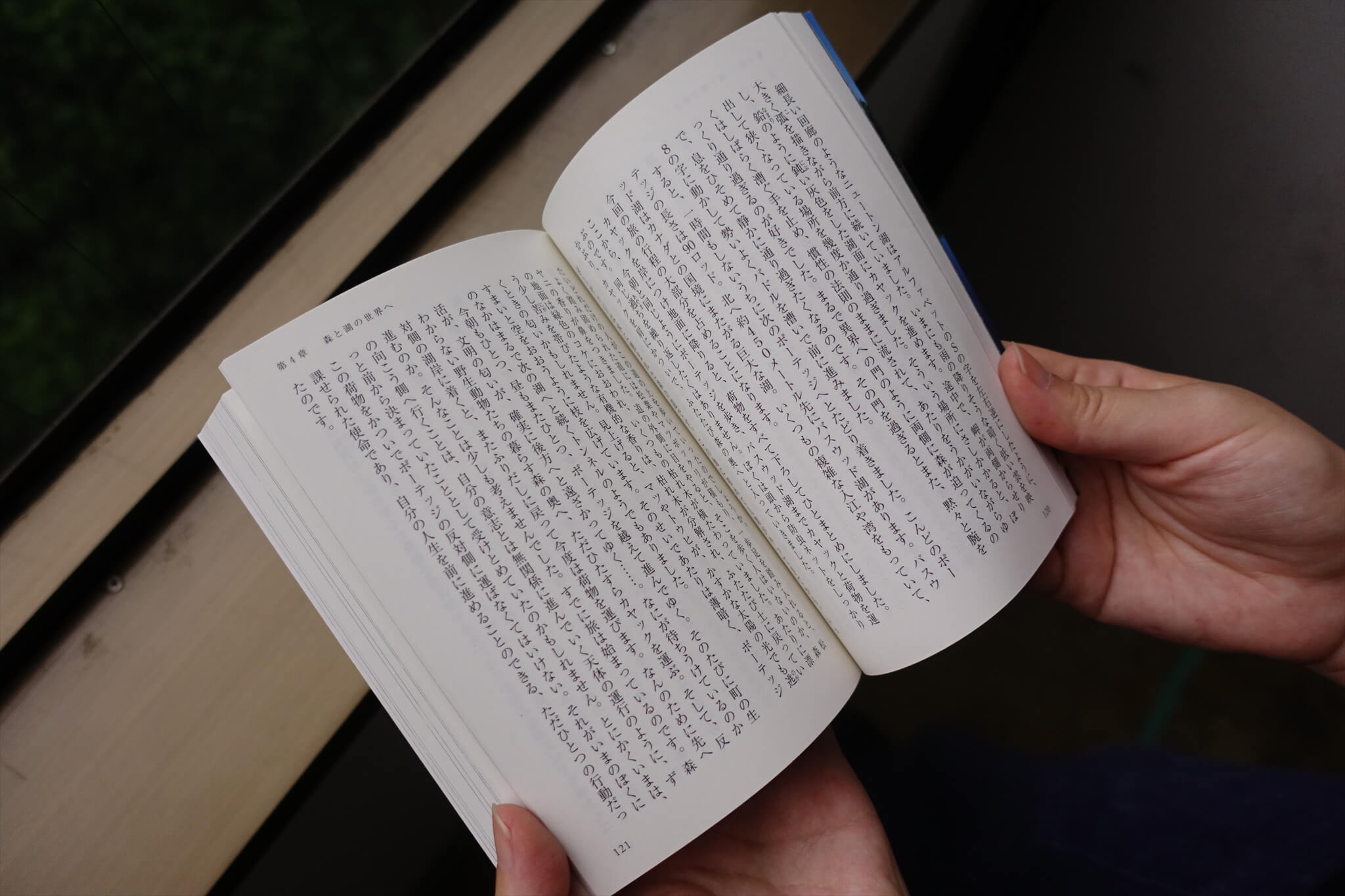
なんのために先へ進むのか。そんなことは少しも考えませんでした。すでに旅は始まっているのです。森の向こう側へ行くことは、自分の意志とは無関係に進んでいく天体の運行のように、ずっと前から決まっていたこととして受けとめていたのかもしれません。
(本文より)
■書籍データ
『そして、ぼくは旅に出た。 はじまりの森 ノースウッズ』
著者:大竹英洋
文春文庫
価格:1,122円(税込)