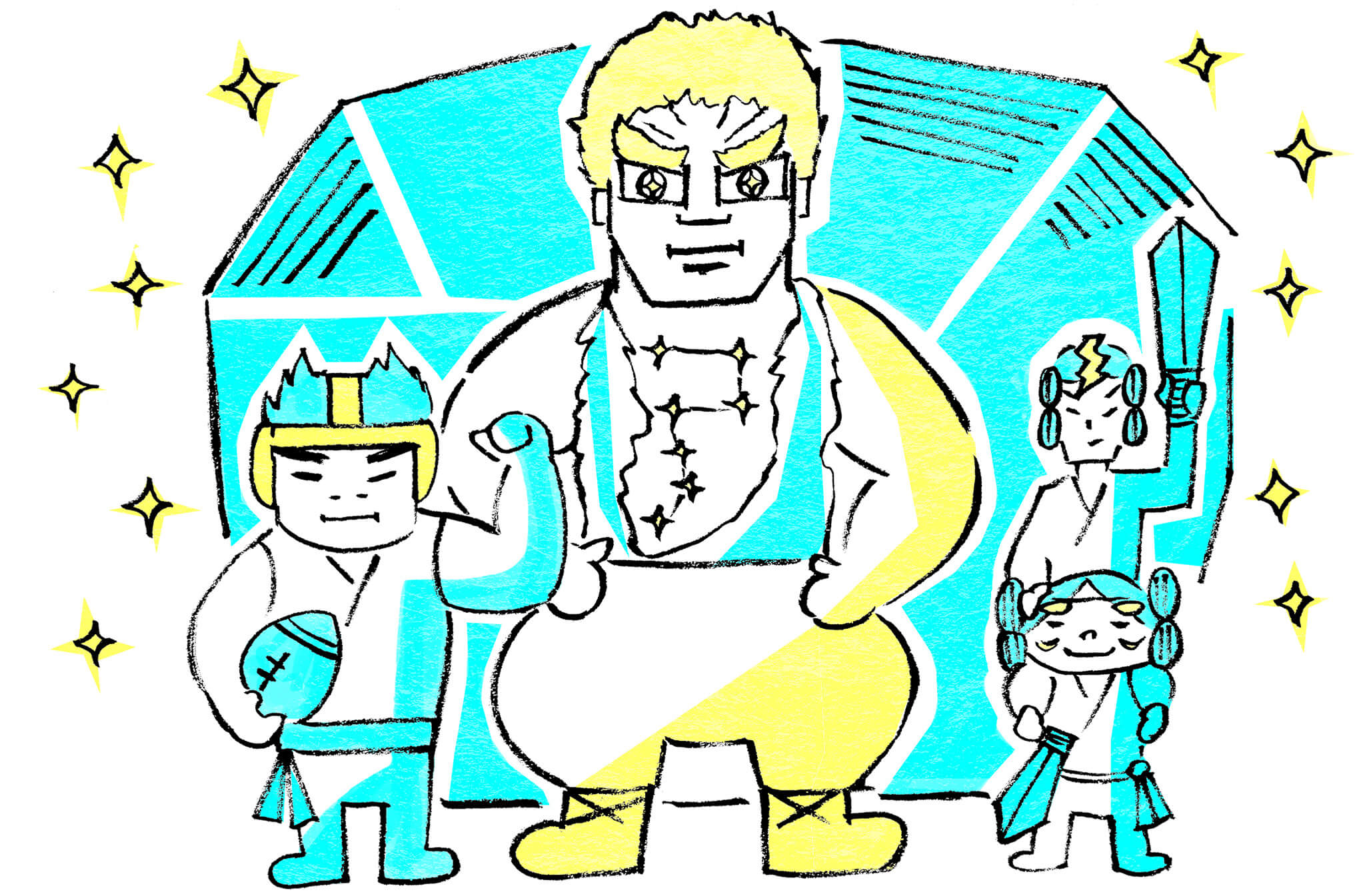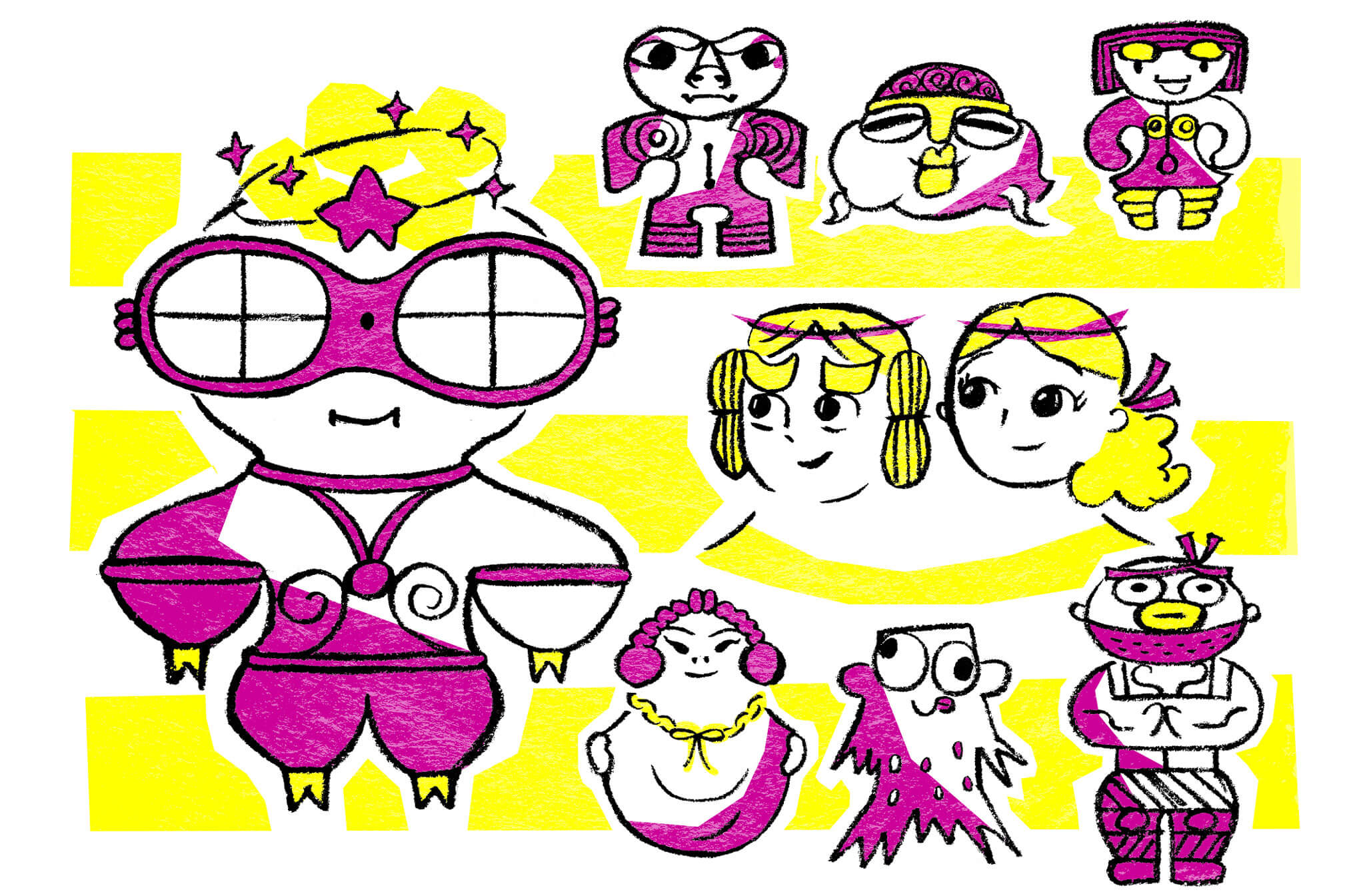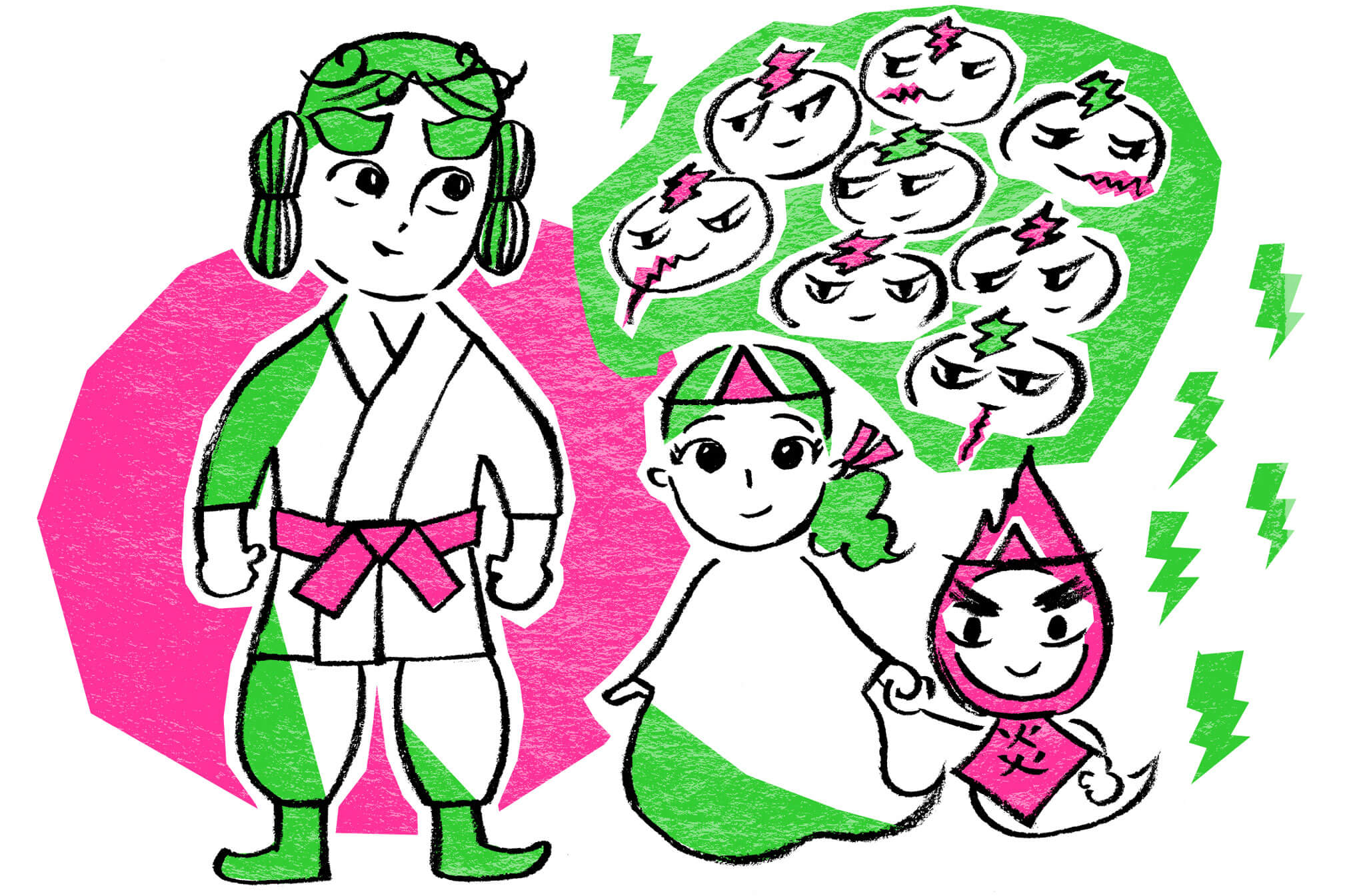日本の森や山には、日本書紀や古事記などの書物にも記された数多の神話が伝えられており、神話のあるところには、同じできごとを違った角度から伝える民話が多く伝えられています。災害が相次ぎ、否応なしに自然と向き合わずには生きていけない今だから。
そんな神話や民話を紐解きながら、物語の中に散りばめられた自然の中に神を見出す日本古来のアニミズム的な信仰や暮らしの術を探求してみることにしました。
常陸の香香背男のおはなし
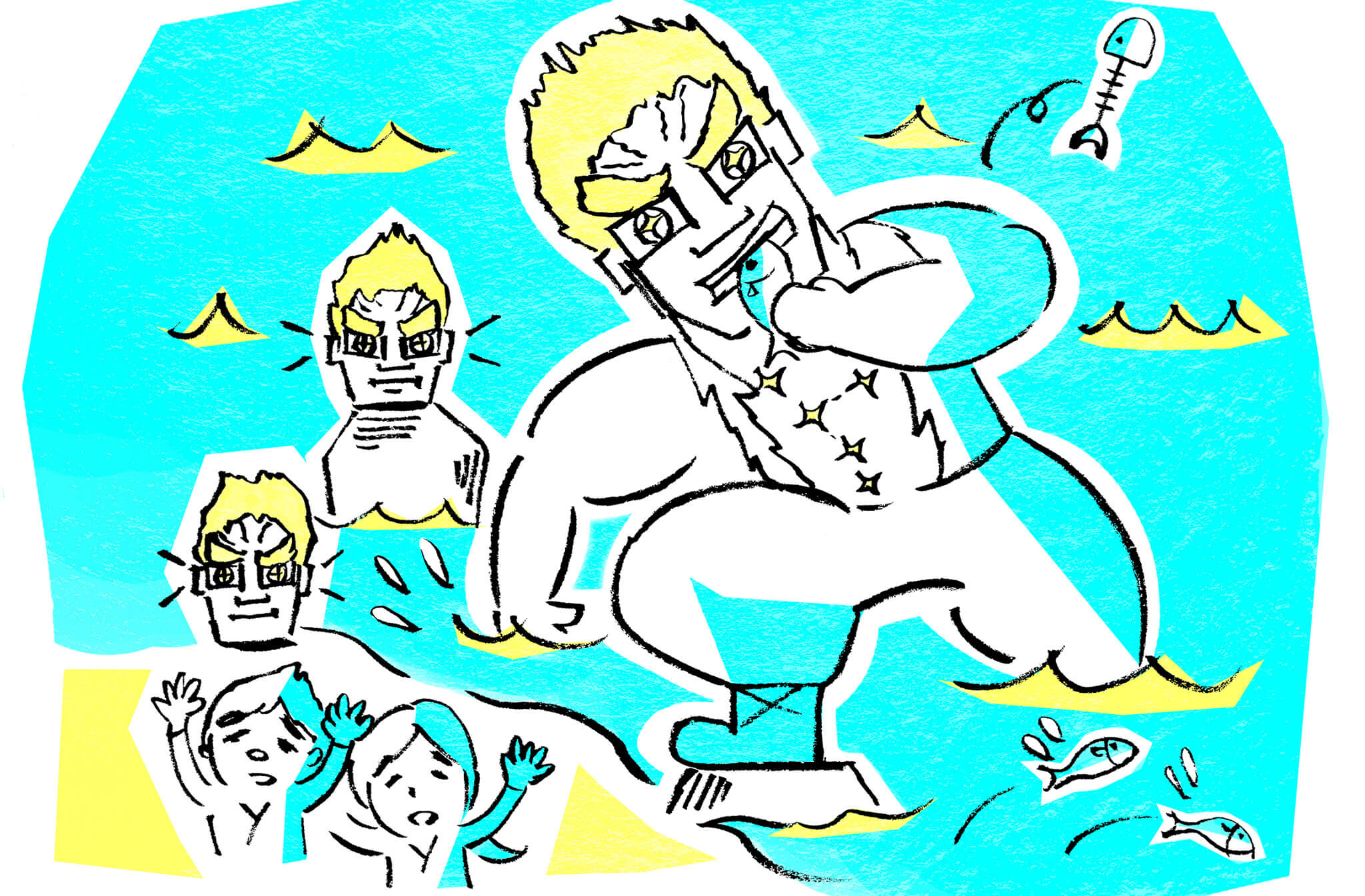
むかしむかし、カミサマたちがこのよのなかにくらしていたころのことじゃった。タカマガハラからぜんこくをヘイテイするようにめいれいをうけたタケミカヅチノミコトとフツヌシは、たくさんのカミサマたちをひきいて、ヒガシへヒガシへとどんどんせめいっておった。
とうとうヒタチノクニ(常陸国)にまではいり、ナカガワとクジカワあたりまでついたときのこと。香香背男(カガセオ)という、メがホシのようにランランとかがやく、キョダイなおおおとこがたちはだかったのじゃ。
香香背男は、ヒルはうみからカオをだすイソカムイワの上をとびまわりサカナやカイをたべあさり、ヨルはオオミカヤマのうえにあるライダンセキのスキマにかくれてイチゾクのものたちをしきしてヒトをおそい、シンシュツキボツ、センペンバンカでさとのたみをなやませておった。
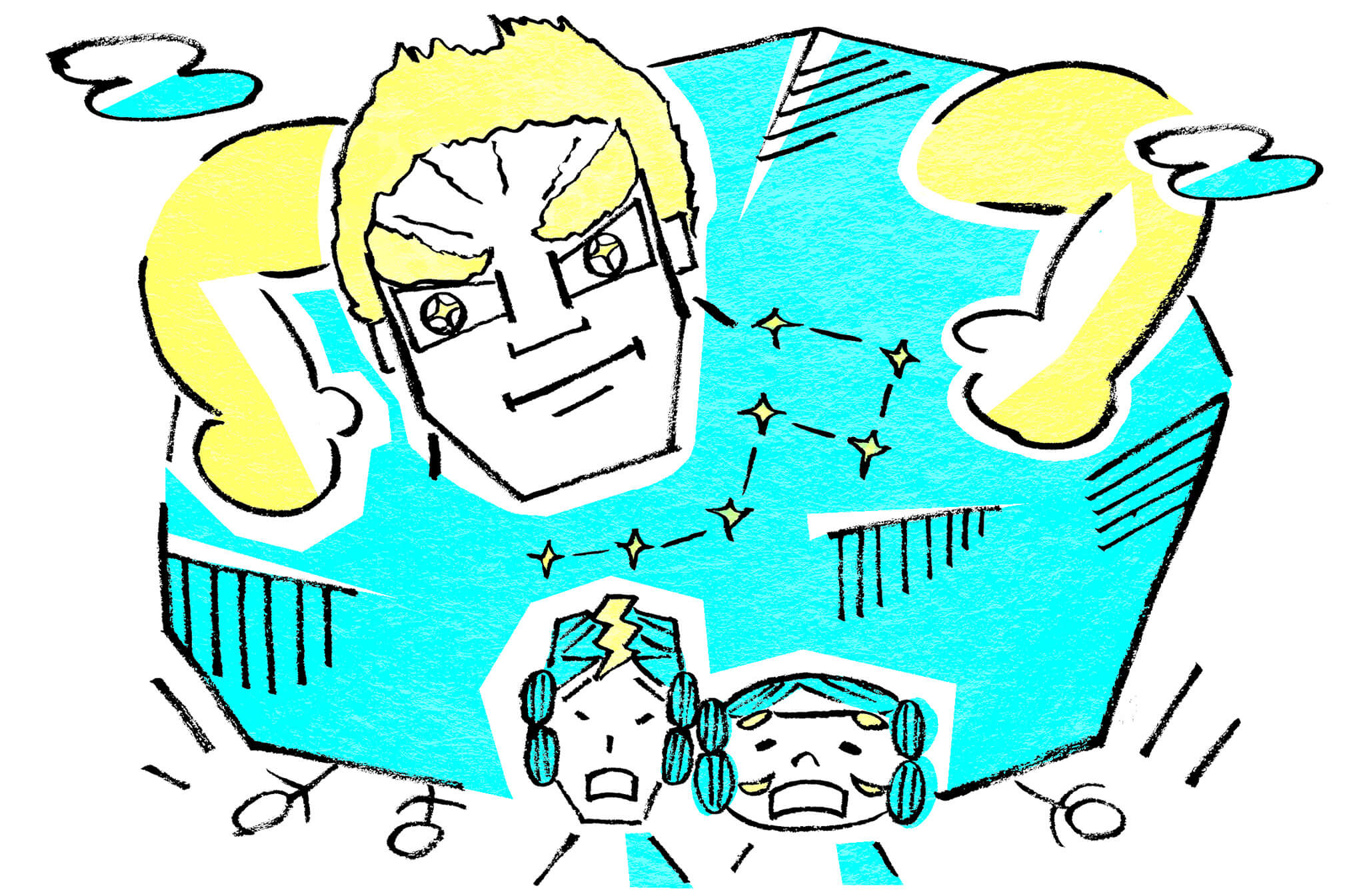
タケミカヅチノミコトとフツヌシのぐんのまえにあらわれた香香背男は、オオミカのさとのイシナザカというところにおおきなトリデをきずいてたてこもり、タカマガハラのぐんはタジタジじゃった。
「いまだ、タカマガハラのこわっぱどもを、ニシへおいかえしてやれい!」
いきおいにのった香香背男は、そうさけぶとスガタをイシにかえ、ヒルにヨルにグングンとおおきくなり、ついにはテンをつきやぶるようなオオイワになってしまったのじゃ。タカマガハラのぐんは、「あんぐり〜」とおどろくばかりで、どんどんそのオオイワにおしつぶされていったのじゃった。
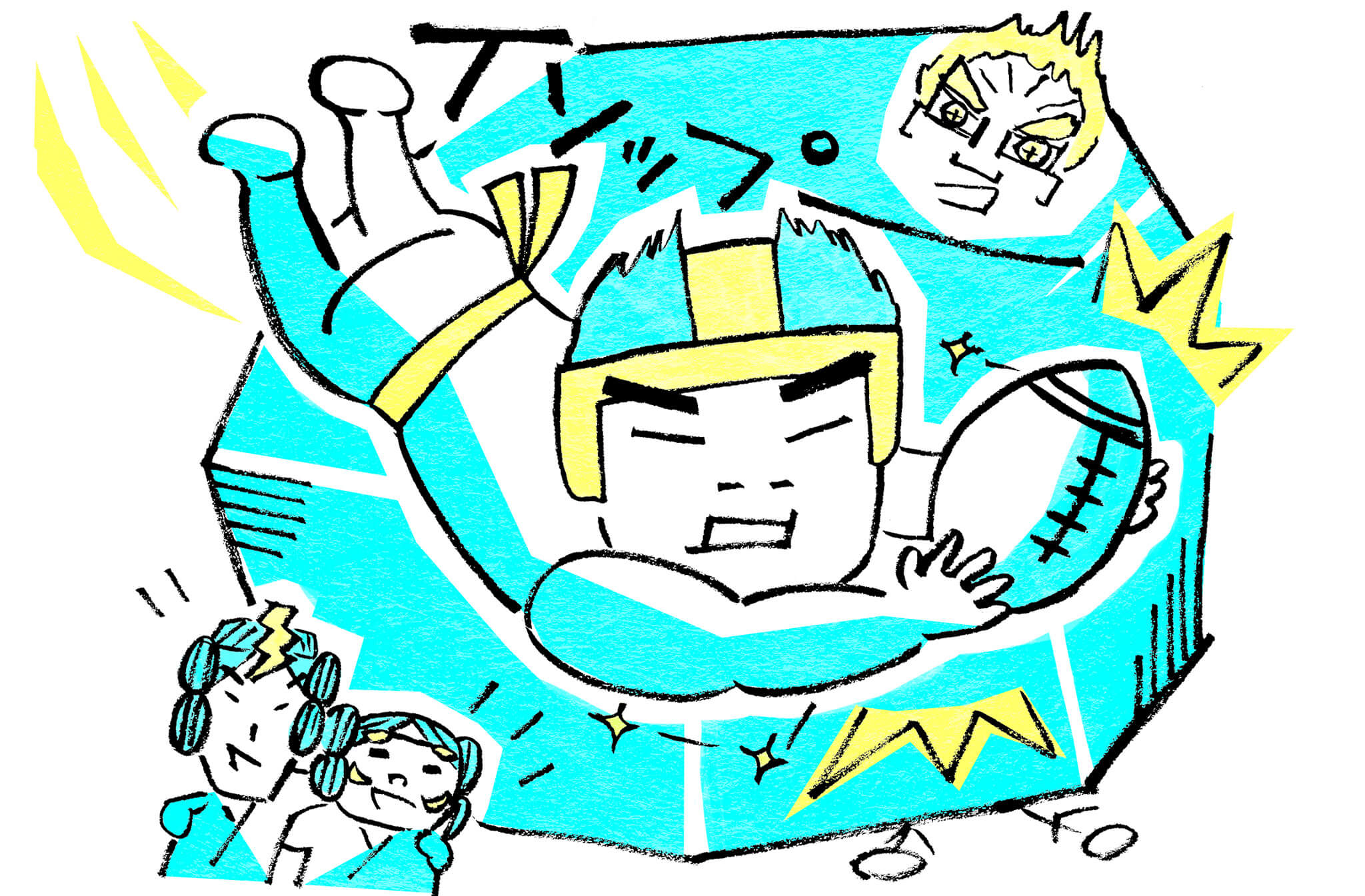
そのころ、オオミカのちかくのシズノサトで、オンナたちにシズオリというオリモノをおしえていた、おおきくてチカラモチ、それでいてジェントルマンなタケハツチノミコトというカミがおった。
タケミカヅチノミコトとフツヌシにイシナザカでのたたかいのようすをつたえきいたタケハツチノミコトは、「わたしでよければ、よろこんで」と、ジェントルにふたりのミカタをかってでたのじゃ。
いままさに香香背男のオオイワがタカマガハラのぐんをのみこもうとしていたときにかけつけてきたタケハツチノミコトは、「香香背男よ、これいじょうのボウジャクブジンは、ゆるさぬぞ。ワンフォーオール、オールフォーワン!」と、まるでラガーマンのようにオオイワめがけてステップをふみながらかけより、オオイワにトライをぶちかましたのじゃった。
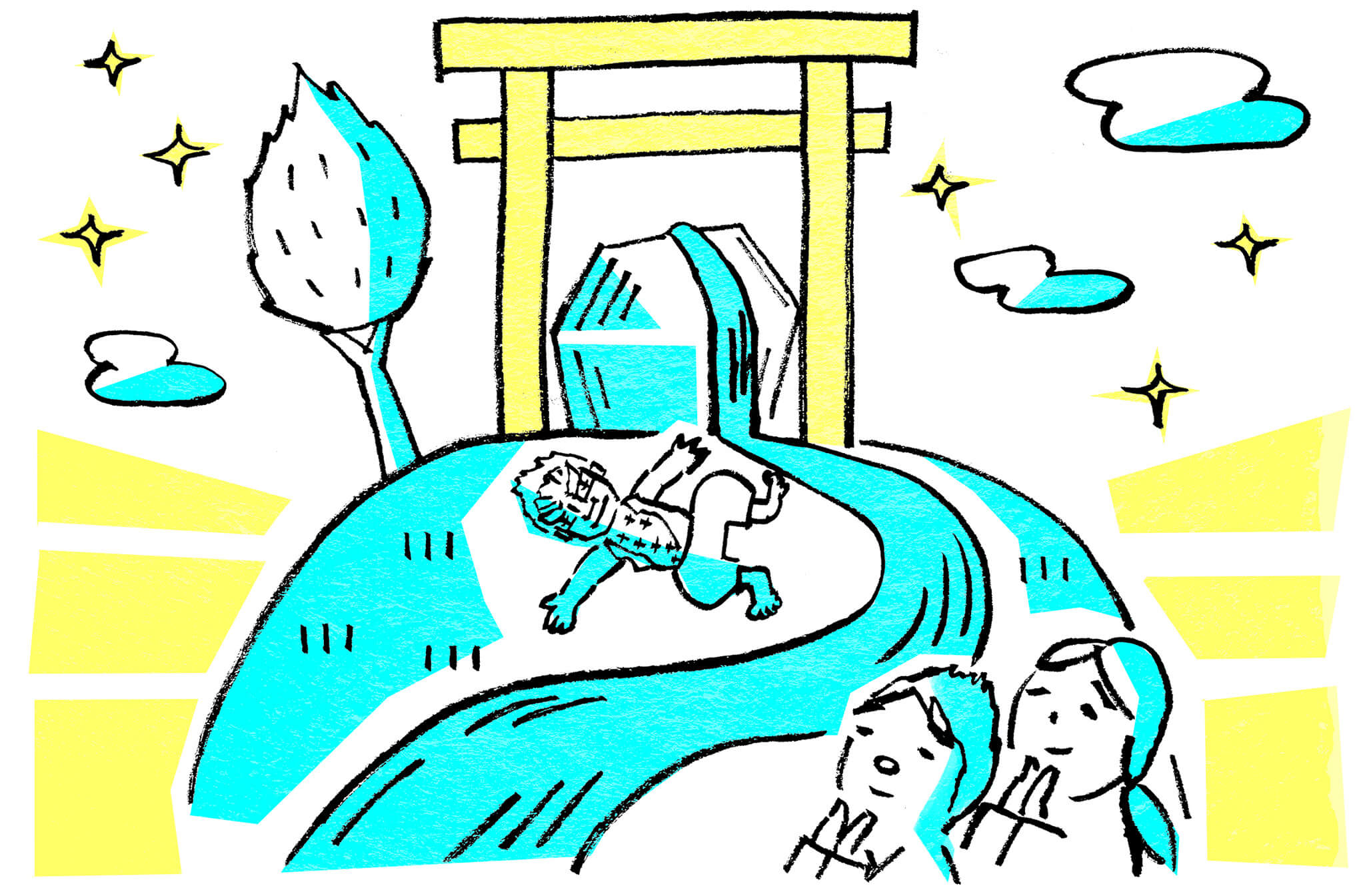
それから、かんどうのビフォーアフターがはじまったのじゃ。香香背男のオオイワはみるみるみっつにわれて、いまのシロサトマチにのこるイシツカ、トウカイムラのイシガミ、そしてカサマにとびちり、じゅつをやぶられた香香背男は、チをはいてそのばでいのちをおとしたのじゃった。
カサマにとんだ岩はひろびろとしたこだかいおかのうえにおちたのじゃ。
なんということでしょう。
するとそこからコンコンときれいなミズがわきだし、やがておおきなイズミとなったのじゃ。
そのちにすんでいたムラビトたちは「なんてきれいなミズなこと。ありがたや〜、ありがたや〜」とそれはたいへんよろこんだのじゃった。
いしがおちたところにみずがわき、イドができ、イズミができていったので、そのムラはイシイとよばれるようになった。ムラビトたちは、そのちかくにヤシロをたて、タケハツチノミコトをまつり、香香背男のタタリをしずめたのじゃ〜。
「香香背男」の解説
上記はカガセオ(香香背男)伝説の地、茨城県・笠間市の石井地区に伝わる民話だ。しかしながら、『日本書紀』には以下の記述があるだけである。
“ある書によれば、天津神はフツヌシ(経津主)とタケミカヅチ(建御雷神)を派遣し、葦原中国を平定させようとした。 その時、二神は「天に悪い神がいます。名をアマツミカボシ、またの名をアメノカガセオといいます。どうか、まずこの神を誅伐し、その後に降って葦原中国を治めさせていただきたい」と言った。”(日本書紀巻第二 神代下 第九段本文)
もともと天津神(アマツカミ=高天原にいる神または高天原から天降った神々の総称)であり、ものがたりで描かれているようにかなり特徴的な神であり、日本神話には珍しい星の神であるのに、なにゆえ『日本書紀』では便宜上触れられている程度なのか。
大枠で言うと、日本人のルーツともいえる海の民にとって、古代、星こそは方角、季節、時間を司る存在であり、海の民は星の神を奉じてきたはずだ。海の民は九州からやってきた一族で、海部、安曇氏という姓を持つことが多く、因みに安曇氏は対馬を旅立ち未開の地・信州を切り開き、長野県安曇野を開拓したと言われている。
『日本書紀』にはまつろわぬ神でありながら天津神と表記されているのは、その後の大和朝廷につながる海の民という点で同じ祖先だったのかもしれない。同じ祖先を持ちながらも朝廷の意に添わない海の民が先に常陸の国を治めていたと考えると、カガセオが天津神であってもおかしくはない。
とはいえ、本気で大和勢力がその地を力づくで奪うなら、「出雲国譲り」で活躍した武神の代名詞として知られるタケミカヅチやフツヌシというふたりの神がもっと活躍したとされていてもよさそうなものの、民話ではカガセオは彼らがかなわないほど強大に描かれ、『日本書紀』に至っては実際に戦ったという記述はなく、同書ではフツヌシの子どもとされる織物の神様=ハヅチノミコトが遣わされたということになっている(因みに二神は石井地区から近い香取や鹿島では祀られているのだが…)。
また現存する大甕(オオミカ)神社にいくと、退治されたガカセオの魂が宿る磐座(いわくら=神の御座所)である宿魂石(シュクコンセキ)の上に、退治したといわれる倭文の神(退治した神様)が祀られているのだが、ここに若干の疑問を感じる。
通常、現地勢力を打ち負かした大和朝廷側は、他の神社などでひっそりと現地勢力の神を祀り続けることはあるが、大甕神社では、ご神体そのものとして対峙されたカガセオの宿魂石が存在し、その上に退治した神が祀られている。つまり、その退治した神様の足元を、退治された神がしっかりと固めて押さえているように感じてしまうのだ。
さらに想像たくましく妄想してみると、同じ天津神であったこと、遣わされたのが織物の神様であったこと、『日本書紀』にカガセオの悪事がどのようなものだったか具体的な記述がないこと、大甕神社ではカガセオが倭文の神の足もとを護っているように祀られていることから、「太陽信仰が進む中で、ことごとく日本の星の神様の存在が消されていき、退治されたカガセオの話が作られたのではないか」と思えてならない。
Profile
中村 真(なかむら・まこと)●イマジン株式会社代表、尾道自由大学校長。『JINJA BOOK』『JINJA TRAVEL BOOK』著者で、自由大学の人気講座「神社学」教授を務める。自然信仰の観点から日本の神社や暮らしの中にある信仰を独自に研究する神社愛好家。信仰と学び、暮らしを軸にした地方活性化プロジェクトを全国各地で展開している。ima-jin.co.jp