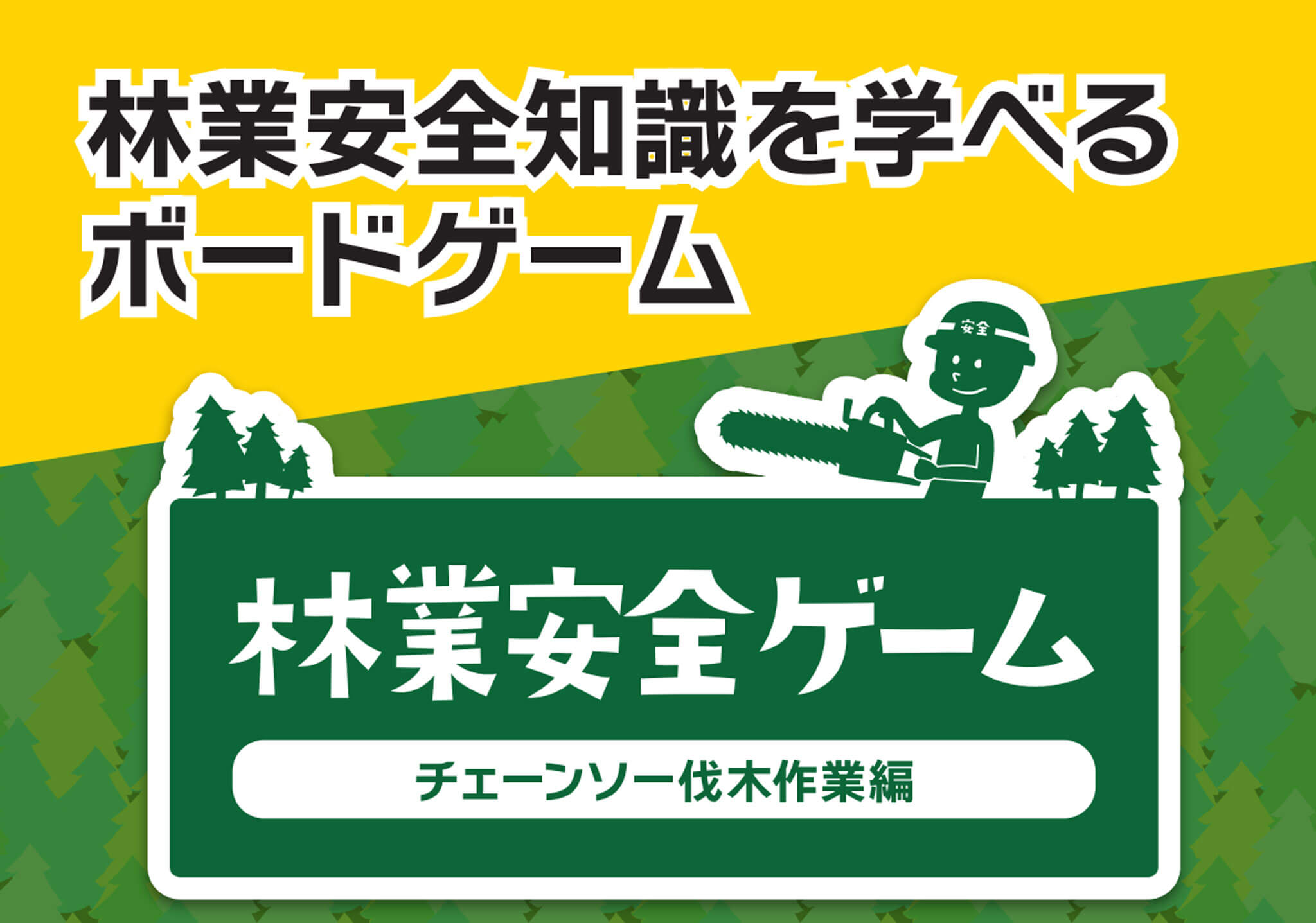間伐などの作業で避けて通れないのが「掛かり木」。その処理作業で、安全性の面から長年、グレーゾーンや禁止事項に位置づけられながらも、現場で連綿と伝わってきた技術が通称「元玉切り」だ。その元玉切りの手順や名称を全国の林業者に尋ねた調査結果から見えてきたものとは?
「必要悪」の技術?
込み入った人工林などで伐採すると、倒そうとした木が周囲の木などに引っ掛かり、途中で傾いたまま止まってしまうことがある。これが「掛かり木」だ。このままだといつ倒れるか分からず危険な上、丸太も採れないので、掛かり木状態を解消する必要がある。
その方法として、公的機関などによる伐倒技術の講習会では、ロープやチルホールなどの牽引器具を使って引き倒すことが推奨されている。また重機が近くにあれば、ウインチのワイヤーを使ったり、重機にワイヤーやスリングを付けたりして引き倒すのが安全だ。

これに対し、「元玉切り」は、引っ掛かって傾いている木の根元付近をチェーンソーを使って玉切りすることで、幹の長さを少しずつ短くして地面に倒す手法。ちょうど「ダルマ落とし」のようなイメージだ。
チェーンソー一台で掛かり木処理ができるものの、傾いている木が作業者自身の方向に倒れてきて下敷きになったり、倒れてきた木を避けようとして斜面から滑落したりする事故が後を絶たない。このため厚生労働省の「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」では禁止事項に位置付けられている。
実際に2017年から5年間の林業での作業別死亡災害発生状況は、林業・林材製造業労働災害防止協会のまとめによると、チェーンソーによる伐木作業中が最多の61%で、このうち掛かり木処理中が32%を占めている。この掛かり木処理で最も危険とされる作業のひとつが元玉切りだ。

https://www.rinsaibou.or.jp/disaster/ringyo.html
しかし現場では「重いチルホールやワイヤーを山で持ち歩くのは非現実的で、元玉切りは必要悪」という声が根強い。このため法令違反となる「浴びせ倒し」と同様に、実際には山の中の間伐現場などは日常的に元玉切りが行われているのが現状だ。
こうした非公然の技術である元玉切りに焦点を当てたのが一般社団法人林業技能教育研究所所長の飛田京子さんら研究者、ベテラン林業者による4人のグループが行った実態調査だ。森林利用学会誌38号(2023年発行)に掲載された。

30種類におよぶ
「伐り方」と「呼び方」
調査は2021年度に開かれた全国の林業技能者向けの研修会で行われ、東北、信越、中部、山陽、山陰、四国、九州の14県の会場で合計260人から回答が寄せられた。ここで明らかになったのが、各地にさまざまな元玉切りの手法が存在し、呼び方も多様性に富む実態だった。
例えば切り方(複数回答)は「受け口あり」が合計180件(49%)、「受け口なし」が合計190件(51%)で、多くの人が使い分けていた。

「受け口あり」のうち、幹の上側に受け口を作る回答は合計298件(26.5%)、幹の下側に受け口を作るのは合計79件(21.4%)となり、引っ張り応力と幹の自重を利用して幹の下側から切り進めたり、細めの木の場合は幹の上側を切り込んで、内側に折り込むようにして倒したりするなど、状況に応じて多様な方法が取られている傾向が浮かんだ。
一方、受け口を作らないケースでは鋸断回数2回が合計140件(37.8%)と最多で、この中には「合わせ切り」にしたり、「ミスマッチカット」にしたりと、さまざまなバリエーションがみられた。これらを含めて受け口角度や鋸断回数、鋸断手順などで分けると30種類に分類され、現場では非常に多様な手法が使われている実態が明らかになった。
また、元玉切りの別称は32種類に上った。同じ呼び方でも実際の伐り方は回答者によって異なるケースが目立ち、例えば「合わせ切り」という呼称の場合、伐り方のバリエーションは10種類に上っていた。
今回の調査は牽引具の使用の有無や掛かっている木の角度、太さといった条件を問わない形で実施したため、飛田さんは「回答者によって想定するケースが異なり、回答数が多岐に渡った可能性があります。ただそれでも地域や事業体によってさまざまな切り方や呼び方が混在している実態が示されたと思います」と話す。

不確実な技術伝搬
によるリスク
多くの切り方や呼称が存在することが明らかになった元玉切り。しかし林業者にとっては木の太さや角度、樹上の状況などに応じて切り方を変えるのはある意味当然だ。それでは今回の調査の意義は何だろうか。
飛田さんは狙いをこう話す。
「元玉切りの禁止については現場との乖離(かいり)が明確で、これだけ現場で活用されているのに止めるのは難しいのが現状です。しかし現実的には村の伝承を唄で伝えるようなアングラな技術として伝達されている。これだと、先輩から見て学べるセンスのあるひとは技術を身に付けられるものの、間違った理解や想像で安易に元玉切りをして事故になるケースも多いとみられます。鋸断手順と呼称の組み合わせの一貫性もない極めて曖昧な定義の中で、本当に禁止させるならその理由を明確にする必要がある。そうした問題を踏まえて、今回はそもそも『元玉切りとは何か』を整理したいと考えました」
これまで存在が基本的にタブー視され、体系的、理論的に語られる機会が極めて少なかった元玉切りに正面から向き合ったのが今回の調査だ。
教育現場や
林業事業体の声は?
林業教育の現場は元玉切りをどう考えるか。岐阜県立森林文化アカデミー准教授の杉本和也さんは「元玉切りは海外では技術として紹介されている場合がありますが、日本の山は基本的に傾斜が急なので、倒れてきた木を避けようとしたときに滑落するなどリスクが高くなる。そうした高リスクの技術を教育現場で教えることは難しいのが現状です。伐倒精度の向上はもちろんですが、アカデミーではヒノキ人工林での実習が多いため、基本的に掛かり木になることが前提での伐採になります。このため持ち運びしやすいフェリングレバーやロープ、場合によってはチルホールなどを使い、元玉切りをしなくても掛かり木処理できる技術を時間を掛けて教えます」と話す。
その上で「例えばヒノキなどの切り捨て間伐で行われるいわゆる『斜め伐り』については、現実的には現場で不可欠なので、胸高直径20センチ未満に限定して教える必要性について県内でも議論が始まっています。元玉切りについても、例えば腰より下の位置で切ることは当然として、現場の傾斜が極めて緩い、また応力の向きがはっきりしているなど、リスク要因が明らかに少ない条件下に限定した上で、公の場での指導内容に含めることの検討は、今後の方向性としてはありかもしれません」と提案する。

林業事業体はどう受け止めるか。山梨県で素材生産や造林、特殊伐採事業を行う有限会社天女山社長の小宮山信吾さんは「元玉切りは社員には禁止しています。しかし技術そのものは『否定も肯定もできない』と考える林業者がほとんどではないでしょうか。なぜなら牽引具などで掛かり木処理を行うにはどうしても時間と労力が掛かる。本来、行政発注の間伐などではそれを加味した上での単価設定がされるべきですが、現状では異なっているからです」と指摘する。
そうした現状を踏まえて「伐倒時の受け口角度や追い口高さについても、より安全に伐るために考え方が変わってきています。それと同じように、元玉切りについても掛かっている木の角度や太さ、切り方、地形などに応じたリスク評価がきちんと行われるべきではないでしょうか。そうすることで、ひとくくりに禁止されている現状が今後変わるかもしれません。そうしたきちんとしたデータの蓄積を現場としては期待したいです」と提言する。
さらなる研究へ
飛田さんらの研究グループは、今回の調査結果を踏まえて、鋸断方法や木の角度など、さまざまな条件に応じた元玉切りのリスク評価を来年度に実施する予定だ。飛田さんは「元玉切りを含めた掛かり木処理は、高い技能が求められる難しい作業ととらえることもできます。しかし危険性を理解せずに安易に行って事故になるケースが多いのが現状。あいまいな定義付けで語られてきた元玉切りの何が危険なのかをはっきりさせるためにも、さらに調査研究を進めていきたいと思います」と話す。
かつて林業会社で働いていた筆者自身も、山の中で先輩から見よう見まねで元玉切りを覚えた記憶がある。その後、別の林業会社から転職してきた先輩は、異なる手順で元玉切りをしていて、状況に応じて切り方を変えることで、より低リスクで掛かり木処理ができる場合があることを知った。同時に元玉切りの危険も何度も見聞きしてきた。元玉切りとは何なのか?どんな場面で危険が高まり、事故が起きるのか?それをもっと知りたいと思うのは多くの林業者に共通する思いだろう。

はじまったばかりの「元玉切り」に関する調査研究。その結果については、自分自身が置かれている立場によってさまざまな意見や評価がある。しかしこれまで明るみに出なかった知見が多くの林業関係者に共有されることが、現場の労災防止に役立つことは間違いない。